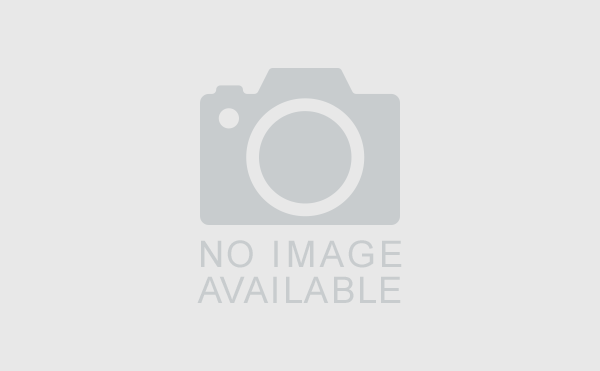【ヤマガラ】在宅 鳥図鑑
| スズメ目シジュウカラ科 撮影月:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |

南側の段々の上の斜面に一本のエゴノキがあります。春先には、メジロ、シジュウガラ、エナガ、コゲラ等がかわるがわる・・・。ヒヨドリ、ガビチョウも、そちらで、高らかな歌声を。5月後半になると、エゴノキは白い花でいっぱい、終日多くのミツバチの羽音が地鳴りのように響いています。やがて、花は実になり、その実を求めて、足しげく通ってくるのがヤマガラです。ヤマガラはエゴノキの実が大好物です。
エゴノキの実の果肉にはサポニンという成分が含まれており、毒性があります。そのため多くの鳥はエゴノキの実を好んで食べることはありません。ヤマガラは、その実、種の部分が大好きです。その場で食べることも多いですが、その実を咥えどこかにせっせと運んで行きます。飛んできては、実を咥え、近くの林の方に飛んでいき、また再び、・・・。数羽がずっと繰り返しています。ヤマガラはその実をどこかに隠してくるようです。あとで、餌がなくなったころ、食べるようです。貯食という行動だそうです。
夏から、エゴノキにヤマガラは現れ、初冬まで、勤勉に働いています。

エゴノキ 
エゴの花とミツバチ 
エゴノキの実

8月 
9月 
10月
留鳥または漂鳥とあります。ここでは、一年中見かけます。エゴノキの時期以外は、シジュウガラ、メジロ等と混群として見かけたり、一羽で高い枝にとまっていたりします。
木の中の虫を探したり、木の実をつついたりすることも多く、大きな音で木を叩くのは、アカゲラ・アオゲラ、小さい音はコゲラかヤマガラです。「トトトト・・・」と音がしたら、ヤマガラであることが多いです。

お尻から 


前から 


下から 
後方から 
幼鳥
雌雄の識別はほとんどできないようです。幼鳥は茶がはっきりしないようで、1枚撮影したものを見つけました。
平安時代から、ヤマカラ、ヤマカラメと呼ばれてきたようです。
鎌倉時代の「夫木和歌抄」に
山がらのまわすくるみのとにかくにもてあつかふは心なりけり
この内も猶うらやまし山がらのみのほどかくすゆふがほのやど
という2首があります。前者は飼っているヤマガラがクルミの実を回しているのを、後者は貯食の習性を詠んだもののようです。(「鳥名の由来辞典」(菅原浩・柿澤亮三編著)より)
ヤマガラは、古くから飼われることも多く、昭和初期ごろまで、芸を覚えさせるようなことも行っていたとのことです。
(2025年8月11日記)
| 撮影年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2022年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2023年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 2024年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2025年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |